弁護士が児童相談所案件に対応します(一時保護、児童福祉法28条審判など)。
一時保護されたとき、知っておくべきこと
0-1.近所の人が誤解して通報した、学校に行っている間にたまたま(虐待とは関係のない)手足のあざやタンコブが見つかった、などの事情で一時保護されることがあります。全くの誤解、つまり虐待が一切ないことがすぐにわかれば、速やかに自宅に返されることが多いです。
0ー2.児相職員が、明確な理由なしに、あるいは、今後の見通しを持つことなく一時保護し施設入所に至ることは、可能性としてはあり得ます。実際にもあるでしょう(私見)。
ただし、ほとんど全てのケースで何か理由があります。全く何の理由も必要性もなく完全な誤解で施設入所に至ることは、「あるかないか」、極めて例外的なことです。
0-3.ですので、もし、あなたが、全く何の理由も必要性もなくお子さんが一時保護されてしまったと考えているとすれば、考え方を少し見直していただく必要があるかもしれません。
児相から見て、あなたが、ご自身や家族の問題に気づかない(気づこうとしない)人に見えるかもしれません。自分自身の問題を改めようとする意思がない=児相の助言に従わない可能性が高い=虐待が継続する可能性があると評価されてしまった結果、親子分離やむなしの判断に至る、となりかねません。
私見ですが、この判断は、一時保護のかなり早い段階で行われているように感じています。
1.児相職員は地方公務員です。子供を家族から引き離すことに個人的なメリットは一切ありません。児相職員に対して、大声やけんか腰で話をして、よい結果が得られることはありません。
1-2ただ、最近の児童相談所は、家庭再統合に向けた活動よりも親子分離に重点を置いているように思われます。どこかは差し控えますが、親子分離自体が児童相談所の目的、存在意義であるかのように振る舞う児童相談所や職員がいます。こうしたレベルの児相は、事実確認もいい加減ですし、児童の発言の裏を取ることもしません。「子供が〇〇と言っているから」で、話が終わり。子供の意思尊重の流れに乗じて手を抜いているのかと疑ってしまいます。数が多いとは思いませんが、たまたま、あなたの地域を管轄する児童相談所が、上記のような場合は、何かを期待するのは、時間的にも精神的にも意味がありません。
2.一時保護は児相が行う行政処分です。解除させるうえで大切なことは、児相の心配を取り除くことです。暴力を正当化する、言い訳や児相批判に終始する姿勢だと、児相職員は心配になってしまいます。現在の実務では、担当ケースワーカーが心配であれば(事実の確認を待たずに)一時保護できると言って過言ではないと思います。警察とは比較にならない幅広い裁量と強力な権限があります。世間の空気もそれを認めています。
3.毎日のように電話をするのは止めましょう。長電話は止めるべきです。児相職員は数多くのケースを抱えており、忙しいです。あなたの話を全て記録に残すことはありません。長電話すると、あなたの良くないところが目立ってしまい、不利なことが記録に残る可能性を高めます。
3-2そもそも、基本的に、児童相談所はあなたの悪いところをピックアップして資料を作成します。そのようにしつけられているのか、それが正義だと思っているのかが分かりませんが、児童相談所の作成する報告書は、そんなものです。そんなものですが、28条審判になれば、家庭裁判所レベルではそのまま受け入れられることがほとんどです。即時抗告して高等裁判所で審理されると、児童相談所が作成した報告書に記載されている事実、そのまま引用するような事はしません。きちんとしてもらえます(ただし結論が変わる事はほとんどありません。)。
4.児相職員に対して「証拠を見せろ」と迫るのは意味がありません。調査するために一時保護したのですから、明確なことを言えるはずがありません。事情を把握している場合も、調査対象である親権者に話すとは限りません(刑事事件に発展する可能性のある場合は、なおさらです。)。公務員は嘘はつかないものですが、知っていることを全部話すとは限りません(守秘義務の観点、プライバシー保護の観点などから抑制的)。
5.児相が行う調査には時間がかかります。一日や二日で児童、学校、親等に対する調査を完了させるのは無理です。児童が落ち着くのに日数がかかる場合もあります。なかなか話をしてくれない児童もいるでしょう。厚生労働省の公開資料によると、一時保護の平均日数は31日程度。兵庫県は全国平均並み。神戸市は14日程度が平均のようです。
6.児相職員との会話を録音し、「言った言わない」、「児相の説明は矛盾している」、「説明がコロコロ変わるから信用できない」、「何も助言してくれない」、その他もろもろクレームをつけることに意味はありません。児相の説明が当初から変わることは多いです。しかし、調べていくうちに分かることもあるわけですから、当初の認識が変わることがあるのは当たり前です。多くの場合、調査が進むごとに、あなたは、どんどん悪い人になっていくことが多いでしょう。
7.お子さんが帰ってくるかどうかは「帰宅させて問題のない養育環境かどうか」です。些末なことで児相と争うのはやめましょう。争うよりもご自分を振り返ってください。自分自身の振り返りをする意思と能力があるか否かは、一時保護の解除において非常に重要です(私見)。
7-2 ただし、時に、児童相談所の職員は、刑事や警察官の真似事のような雰囲気で、色々と聞いてくることがあります。露骨な疑いの言い方でいろいろと質問されることがあると思います。腹が立つでしょうが、大声を張り上げないように気をつけてください。
8.一時保護に至った主要な原因が親には無い場合は多くあります。養育が非常に難しい児童もいるでしょう。しかし、その場合も児童の立場に立てば、養育環境には何らか問題が生じていることが多いです。問題を認識し、原因について考えようとする姿勢を見せてください。
9.自分の問題点は、自分では分かりにくいものであることを前提に、児相職員の話をまずは聞いてください。頭から否定するのではなく、聞いて、理解して、自分で考えて行動していただくことが重要です。 ただし、何を言っているかよくわからない職員はいます(どこの会社、団体でも、そういう人はいます。)。その場合でも切れないようにしてください。
9-2 物を考えて喋っているのかどうか、単に報告書を作成して、ファイルに綴じるのが仕事だと思っているのではないかと、疑問に感じる職員も割といます。そもそも、児童相談所の職員は、調査の目的や見通し、終着点等について説明しません。広範な裁量があることを盾にとって、説明義務がないと勘違いしている職員もいます。今時の行政指導ではありえない説明のなさです。
10.地方議会の議員に児相に対する働きかけを依頼しても効果はありません。印象としてはかえってマイナスです(私見)。
11.不服審査申立は、ほとんど確実に期待できません。一時保護期間が延びるだけです。第三者機関のある自治体ならそちらを利用すべきです。一時保護延長の承認審判もほとんど期待できないと思いますが、児相側が資料を出してくるので、ようやく全体像がわかるメリットはあります。
12.一時保護されると例外なく施設入所になると心配する方がいますが、そうではありません。厚生労働省の公開資料によると、2019年の一時保護件数は全国で約5万件。同年中の解除件数が約3万件、解除後の施設入所は約5000件です。
13.当事務所は、一時保護の早期解除のためには、①暴力や暴言・ネグレクト・態度による無言の抑圧等を認めて、②反省し、③改める、の3ステップが基本的に重要かつ必要と考えています。しかも、一時保護直後の初期の段階で、児相職員に分かってもらう必要があるように思われます。私見では、児相は、かなり初期の段階で心証形成します。
14.原則として、児相には正直に話をすることをお勧めしています。しかし、虐待事案は刑事事件に発展する場合があります。監護者性交罪のように、長期服役が予想される類型の事案もあります。児相には黙秘権の告知義務はありません。他方で、深刻な事案では警察と情報交換していると考えてください。的確な助言をするため。弁護士との相談時には、不都合な事実も隠さずに話していただくことをお勧めします。刑事事件になり得る場合は児相問題と全く別の対応が必要です。受任しない場合も当然ですが秘密は守ります。
15.ご夫婦で相談に来られることが多いですが、利益相反する可能性がありますから、一人で相談に来ていただくことを強くお勧めしています。ご夫婦で来られた場合、後日意見や利害関係が対立した際、どちらか一方の代理になることはできません。なお、親権者以外の方(例:児童の祖父母)が同席しての相談は、例外なく全てお断りします。
16.経験上、もう少し早く相談してくれていればと思うことが大変多いです。
現状、児相は家庭再統合ではなく、虐待事案の摘発、親子分離に軸足を置いているように見えます(私見)。
一時保護された初期の段階で的確に対応することが非常に重要だと考えています。
17.最後に、継続してご相談に応じる、あるいは、代理人として児相協議に同席する場合は、安いとは言えない弁護士費用が掛かります。詳細は最後の費用のページをご覧ください。
【お願い】初回お問い合わせはメールでお願いします。電話相談は、例外なくお受けしません。
児相案件は、離婚問題等と比較しても手間がかかるうえ、刑事事件以上に迅速な対応が必要なことがあります。
受任弁護士としても大きなストレスがかかります。
事務所経営的には、率直に申し上げてマイナスです。
このため、弊所で実際にお受けしているのは、ご相談をいただいたケースのごく一部です。
お受けできないことの方が多いのが実態ですので、あらかじめご承知おきください。
弊所は、気軽に法律相談できる事務所づくりに努めておりますが、児相案件は慎重に対応せざるを得ませんので、まずはメールでのお問い合わせをお願いしております。
1.児童相談所との交渉や家庭裁判所の審判等への対応について、法律相談をご希望の場合、または児相協議への同席依頼等をご検討の場合は,メールで,①から⑩の基本情報を連絡してください。
面談相談日等について、お送りいただいたメールアドレスに返信します。
なお、メールでの相談対応は行っておりません。電話相談は、遠方の方についてお受けする場合があります(その場合もまずはメールでご連絡お願いします。)。法律相談は有料相談となります(費用はホームページの下の方)
2.メールの件名は,「児相案件(お子さんの氏名)」としてください。(お子さんの氏名)ですが、複数のお子さんが一時保護された場合は「〇〇〇〇ほか〇名」等と記載してください。
① あなたの住所、氏名、連絡先電話番号
② あなたの生年月日
③ 一時保護等されたお子さんの氏名及び生年月日
④ ③のお子さん及び保護者の心身の健康状態(障害の概要等)
⑤ 家族構成(あなた及び③のお子さんを除くご家族(例えば配偶者、児童の兄弟姉妹)の氏名と年齢)
⑥ 児童相談所名
⑦ 一時保護の年月日
⑧ 一時保護の理由について、心当たりがあること
⑨ ⑧に対する、あなたの意見・言い分
⑩ 現在の段階(一時保護中(以前にもあれば、何回目か),一時保護延長打診、一時保護延長審判申立、施設入所打診,28条審判申立,即時抗告,施設入所(里親)済,その他(親権停止・喪失審判等))
⑪ 法律相談(面談)の希望日時 できれば3日ほど、希望日時をお願いします(原則として平日10時~17時)。遠方の方は電話相談ご希望日(お急ぎだと思いますが、当日対応困難なことが多いです。)
3.時系列メモ作成のお願い
法律相談のため来所される場合は、一時保護決定書、時系列でまとめたメモなどを持参していただければ、効率的にご助言できます。
※次のボタンをクリックしてください。
児童相談所の業務、一時保護等についての一般的な情報(参考webサイト)
1.児童相談所の業務内容全般について
東京都が公開している「児童相談所のしおり」が詳しく、参考になります。
2.児童虐待に対する児相の対応
現状、児相の判断は、親権者から見るとブラックボックスです。
そんななかで、公表資料に手掛かりがあります(推測ですが)。厚生労働省のHPに掲載してある、「子ども虐待の手引き」です。
厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き」は、児相と話をする際の参考になりますし、ご自身やご家庭で、養育環境などを振り返る場合にも、考えるヒントになります。
このうち、第5章が、一時保護についての記載です。
児相が一時保護を決めた理由を知るヒントになります。
(1)一時保護の目的
第5章は「1.一時保護の目的は何か」から始まります。
そこには、次の通り書いてあります。
【第5章 1.一時保護の目的は何か】
「一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することである。単に生命の危険にとどまらず、現在の環境におくことが子どものウェルビーイング(子どもの権利の尊重・自己実現)にとって明らかに看過できないと判断されるときは、まず一時保護を行うべきである。
一時保護を行い、子どもの安全を確保した方が、子どもへの危険を心配することなく虐待を行っている保護者への調査や指導を進めることができ、また、一時的に子どもから離れることで、保護者も落ち着くことができたり、援助を開始する動機付けにつながる場合もある。
子どもの観察や意見聴取においても、一時保護による安全な生活環境下におくことで、より本質的な情報収集を行うことが期待できる。
以上の目的から必要とされる場合は、まず一時保護を行い、虐待の事実・根拠はそれから立証するという方が子どもの最善の利益の確保につながりやすい。」
【第5章 1.一時保護の目的は何か からの引用は以上】
このスタンスであれば、事実上、児相職員が心配だと感じれば一時保護することになるでしょう。
もちろん組織としての決定にはなりますが、児童や親と対面した職員の意見あるいは報告書の判断が優先されるはずです。
実際に見てきたものに対して、反対することは難しいものです。
(2)一時保護をする・しないの判断ポイントなど
第5章に掲載されている「子ども虐待対応・アセスメントフローチャート(図5-1)」は、一時保護の流れ図になっています。
表5-1の「虐待相談・通告受付票」とわせて、参考にしてください。
また、図5-2「一時保護に向けてのフローチャート」は、一時保護を行う判断ポイント(例えば、重大結果の可能性、繰り返しの可能性など)が分かります。
表5-2「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」は児相のチェック項目です。
児相が何を考えて(何を心配して)一時保護をするのか、推測するヒントになります。
|
||
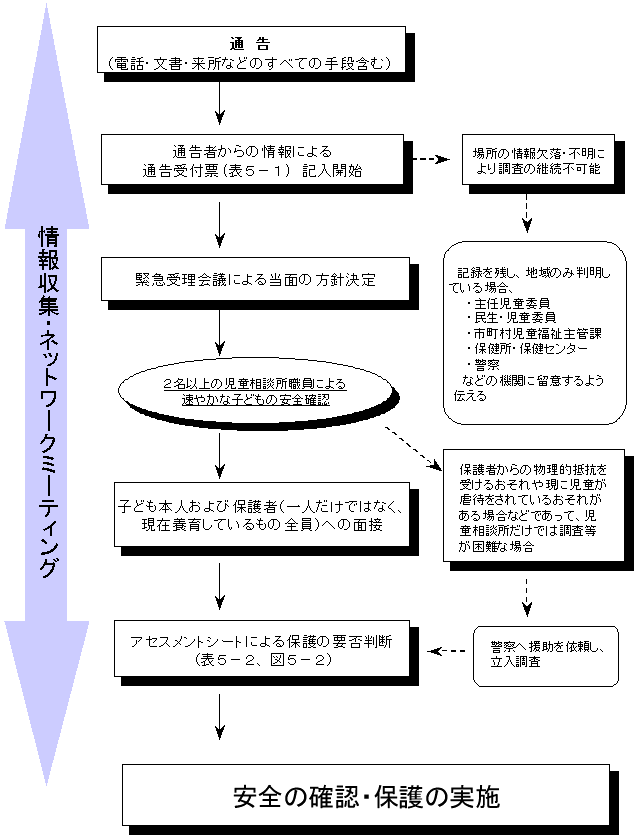
|
|
聴取者( ) | ||
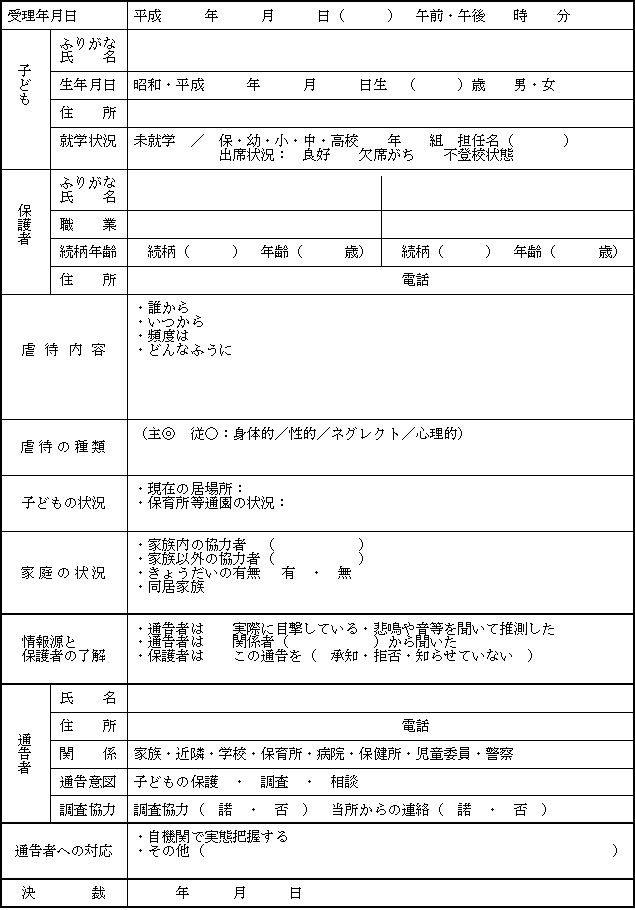
|
|||
| 表5-2 | 一時保護決定に向けてのアセスメントシート |
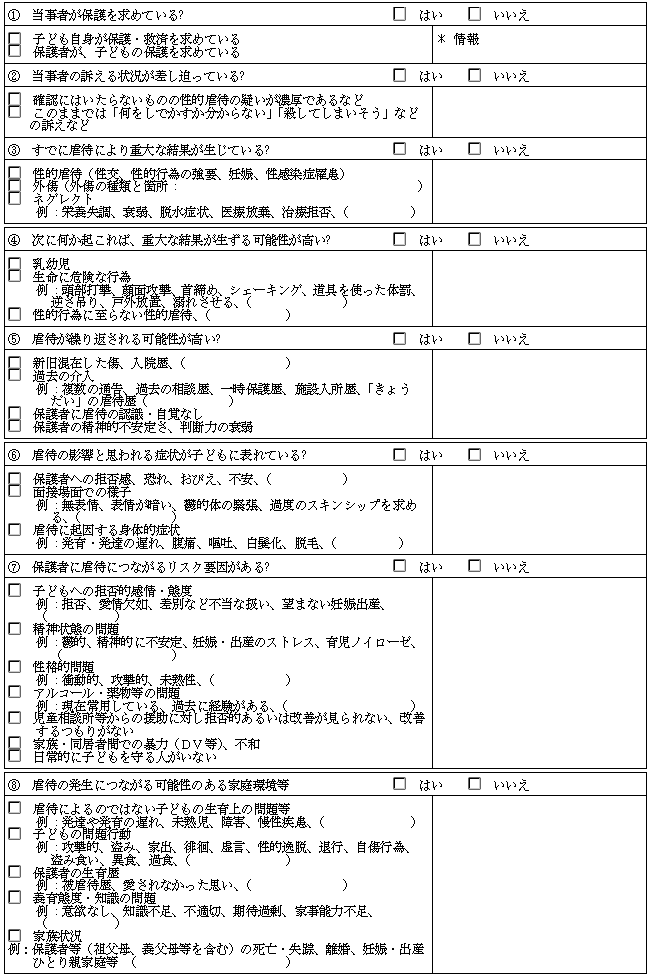
| 図5-2 | 一時保護に向けてのフローチャート |
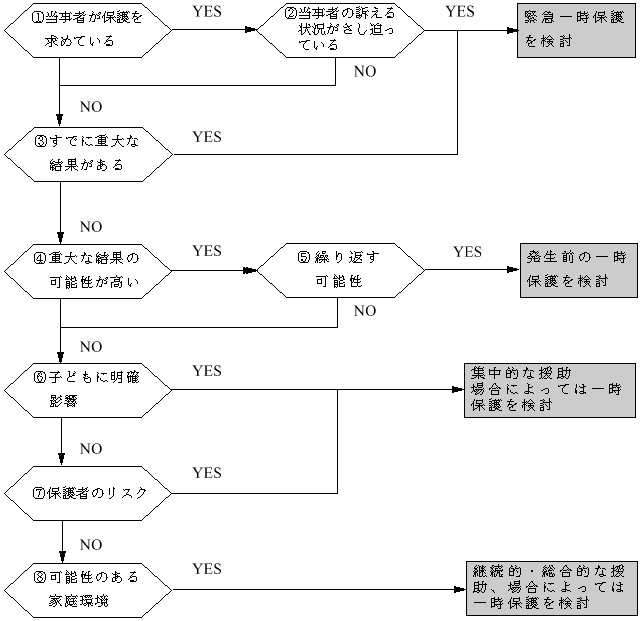
(解説)
|
(3)施設入所の判断
第6章に、「親子分離の要否評価チェックリスト」があります。
児相が一時保護の後、家庭に戻さず施設入所方向に判断する際の判断の重要ポイントとして参考になります。
資料出所:「子ども虐待対応の手引き 第6章 表6-1
|
「 |
親子分離の要否評価チェックリスト(現在の状況および将来予測される状況)」 |
|
下記の事項に該当する場合親子分離の必要性が高い
(高橋重宏・田中島晁子・中谷茂一) |
当事務所の業務(概要)
1.弁護士がお手伝いできること
(1)児相との交渉の代理人業務
児相に書面を送ったり、依頼者と児童相談所との協議に同席し、家庭復帰のサポートをします。
児相との協議の前に、児相が気にするポイントをご説明し、依頼者の言い分や希望が児相職員に伝わるよう事前に打ち合わせをします。
※児相に対して、その場限りの嘘を述べる、迎合して話を作る・盛る、法の抜け穴を探す等は、かえって解決を遠ざけます。そもそも、お子さんのためにも依頼者のためにもならないので、しないようにお伝えしています。
(2)裁判所の手続きにおける代理人業務
親権者が、一時保護の延長や施設入所などに同意しない場合、児相は,親権者の同意に代わる承認を求めて家庭裁判所に審判申立をします。家庭裁判所での手続きです。
その手続きの代理人として、答弁書や意見書の作成、審判への出席、結論に不服のある場合の高等裁判所への即時抗告などの事務を行います。
各論(具体的な方法・手続き)と当事務所の業務
Ⅰ 一時保護解除のための具体的な方法①・交渉段階
一時保護決定書には、決定を不服とする親権者のために、行政不服審査や行政事件訴訟について簡単な説明が書いてあります。
親権者の中には、直ちに審査請求を申し立てる方もいます。それ自体は間違った方法ではありません(児相は時間を取られるので嫌だとは思います。)。
審査請求、あるいは行政事件訴訟は、重要な点で明らかな事実誤認があるケース、つまり刑事事件でいう冤罪ケースでは、申請請求を申し立てたほうがよいこともあるでしょう。
しかし、弊所は、裁判手続で争う方法は、多くの場合、ベストではありません。
裁判所の手続きに移行する前の段階、すなわち、児童相談所と話し合う段階が一番重要です。
その段階に注力する方が、早期に家庭に帰ってくる可能性が高いからです。
1.児相との交渉段階
(1)法的紛争になる前の解決が現実的
① そもそも、行政機関である児相には、広範な裁量が認められています。
家庭裁判所で争った場合も、児相の言い分を全部認めなくても、結論として、「児相の裁量に逸脱はない」とされやすい傾向にあります。
また、長期の一時保護や施設入所が必要とは考えられないケース、家庭復帰の方が適切だと考えられるケースであっても、何らかの問題が背景にある場合は、児相と協力して継続的に対応していく必要があります。
さらに、当事者にとってはつらいことですが、親権者が大変頑張って養育されているケースであっても、児童自身に、専門的な指導訓練や医療措置などが必要な場合もあります。
こうした場合、児相の協力を得て、時間をかけて問題解決することが必要です。
② 養育環境や児童の特性に何らかの問題がある場合、児童相談所との継続的な協力関係の構築はが必要となってきます。誰が悪いわけでなくても、必要なことは必要です。
したがって、一時保護されたお子さんの家庭復帰を早期に実現するためには、仮に、結果的に一定期間の施設入所がやむを得なくなったとしても、児童相談所との(できるだけ良好な)関係性を保つのが望ましいことになります。
児相と話し合い、家庭復帰後の生活環境に問題がない環境づくりを進めていく必要があります。
その前提として、問題解決のために親権者が継続的に努力すること等を、児相の職員に理解してもらうことが重要です。
③ ただし、事実誤認がはなはだしく、間違った認識に基づいて施設入所措置をしようとしている場合には、法的な対応が必要です。
(2)児童相談所と、どう向き合うか(基本的な対応)
① 一時保護直後の親権者
子供が一時保護された親権者の多くは、何から手を付ければよいか分からない状況になりがちです。
一方の親権者が気付かない間に、他方親権者(配偶者)がお子さんを虐待していたケースでは、離婚問題に発展することもあります。
全く解決の道筋が見えなくなることもあります。
② 児相職員と親権者の関係
児相職員は、非常に忙しいです。
かなりの長時間勤務、時間外勤務をしながら、仕事をしています。
出張や面談をした後、デスクワークも膨大にあります。
職員一人で数十人を担当し、忙しい中、次から次へと、既存案件と新規案件に対応しなくてはなりません。
限られた時間で、子どもを落ち着かせ、じっくりと話を聞かなくてはなりません。
親権者から話を聞くのは後回しになりがちです。
話を聞いてくれたとしても、基本的に、親は「調査対象」です。前提事実は、子供が発する言葉が基本です(誘導的になされるケースもあるようです。)。
親権者が、「どうしたら、子どもを返してくれるのですか?」と尋ねても、明確な回答が返ってくることはありません。
一時保護期間中、特に初期には子どもとの面会はできません。
この辺、本当によくわからないのですが、また、率直に言って、違法不当なの面会制限としか思えないケースもよく目にするのですけれども、実務上、担当ケースワーカーの抽象的な不安感が払拭されない限り、面会制限が続きます。
親権者は、情報も入らず、児相からは疑いの目で見られ、何を話しても「現実を見ていない」「自己を正当化する」等と決めつけられるように感じます。
子育てに悩み児相に相談したことを契機に一時保護されるケースでは、児相に裏切られた気持ちになります。
悩みを相談している最中に、例えば「このままでは何をしでかすか分からない」「殺してしまうかもしれない」等の発言があれば、一時保護に直結しますし、施設入所方向に大きく傾く可能性が高まります(アセスメントシート②参照)。
児相に相談したばかりに、子供と引き離されたと思っている方は多いと思います。
③ 悪循環
一時保護された後は、児相に対する疑念が膨らみ、反感が強まり、児相職員との冷静な話し合いが困難になっていくことがあります。
大きな声で児相職員に詰め寄ったり、頻繁にかつ長時間、電話をかけてしまうことがあります。
こうなると、物事が悪い方へ悪い方へと進みます。
児相職員から見れば、「自分を顧みることのできない親のいる家に、帰すわけにはいかない」となってしまうかもしれません。あくまでも児童目線ですから、帰宅させると児童の安全安心が確保できないと結論づけられてしまうリスクを高めます。
ケースワーカーらが作成する書類(報告書の類)にも、親権者のマイナス面が強調される可能性も高まります。
その資料は、28条審判の証拠資料として使用されます。
28条審判が却下になる可能性は、低いです。高い確率で、施設入所が認められます。
最高裁の公表資料によると、平成26年度、全国の家裁で合計267件の処分が行われ、うち認容が211件、取下48件に対して、却下は僅か6件でした(残り2件はその他)(次の最高裁HP参照:PDFファイル)
最高裁公表資料「児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情 平成26年1月~12月」
④ 児相との接し方(基本的姿勢)
児相の職員は、いたずらに親子を分離しようと考えてはいません。
できるなら、早期に家庭復帰させたいと考えているはずです。
児相職員は公務員であり、件数を上げれば給与が増えるわけでもありません。
この仕事が大好きな職員は、ほとんどいないと思います。
件数を上げて昇進したいと考える職員も、いないと考えていいと思います(そういった組織ではない。)。
件数を上げれば国からの補助金が増額するからノルマがあると思っている方がおられますが、そのようなことを気にする職員は、まずいません。
予算、行革、監査などは、本庁の管理部門の一部の者が気にすることで、現場の一般職員には関係のないことです。
ただし、地方公共団体が運営する施設の定員については、行革の対象や監査の指摘事項になるリスクを気にする場合はあり得るかもしれません(一定数の確保など)。
児相職員は、通報を受けた場合や、相談に来た親権者の話から一時保護が必要と判断した場合、「仕事として」動きます。
問題がある家庭で養育されている児童はたくさんいますが、行政が実際に関与するケースはごく一部です。
役所には、「知ってしまったら関与せざるを得ない」面があります。
そして、いったんかかわると、児相の職員は決まった方針に沿って対応します。
マニュアル通りに、聴取項目を親権者に質問しています。
仕事として事情聴取するのですから、それに対して文句を言っても意味がありません。
児相職員の負担を増やすだけで、有利になることはあり得ません。
ですから、児相での面談、特に初回の面談では、まずは児相の職員の説明や質問に耳を傾け、話しを聞くことが大事です。
その際の注意事項として、最低限、暴力を絶対に正当化しないこと、一時保護の理由について思い当たる事実を考えてみること、言い訳に終始せずふりかえって改善すべき点があれば改善する意思があることを示すこと(自分を振り返ることなく一方的に子供を返せと言わないこと)は、留意するのが賢明です。
自分一人では解決できない場合は児相を含めた関係機関を頼り、子どもが家に帰ってくるための環境整備を行なってください。
関係機関が関与したから状況が悪くなったと考えている方も多いと思われます。
子供一人一人には特性があります。
児相職員と話すのが苦痛な児童は存在します。単純に、家庭の中のストレスで話ができない状態だなどと決めつける職員がいないとは限りません。
法律相談ではよく聞く話です。
しかし、それでももう一度、冷静に振り返ってみましょう。
児相からは、「長期にわたる不適切な親子関係の改善」など、抽象的で具体的に何をどう改善すればよいのか分からない、かえって混乱する助言しか得られない場合があります。
むしろ、その方が多いように見受けられます。
このことが、児相と親権者間がこじれてしまう原因の一つだと思われることがあります。
しかし、だからと言って話し合いを中断するのは、解決を遠のけます。
⑤ 弁護士の支援が効果的なケース
児童相談所は都道府県や市役所の地方機関の一つで、大きな組織ですから、人事ローテーションもあります。
職員にも様々な方がいます。民間企業と同じです。
ほとんどの職員の方は熱心で親切ですし、公平・冷静ですが、コミュニケーション能力や事務処理能力に、いささか問題がある職員がいるかもしれません。
熱心さのあまり思い込みの強い方がいるかもしれません。
人間同士なので、性格が合わないこともあります。
さらに、どんな組織でも同じですが、担当ケースワーカーは常識的な職員であっても、上司に問題のある場合もあり得ます。
管理監督職に、関連知識も、やる気も無い人が来ると、担当者も大変です。
また、組織はどうしても、一度決まった方針を変えにくいものです。
こうしたこともあり、いったん施設入所の方向に傾くと、早期の家庭復帰に向けた話し合いの余地が狭くなりがちです。
コミュニケーションがうまく取れないなど、悪い条件が重なると、児相と普通に話をすることすら、しんどくなってきます。
お子さんが急にいなくなって、冷静に対応すること自体が大変なのに、児相職員と円滑に話ができないと、疲れてしまいます。
児相との冷静な話し合いが難しい場合は、弁護士の関与が役に立つ場合があります。
⑥ 児相との交渉段階で、弁護士が介入するメリット
弁護士は、裁判をするだけではなく、様々な交渉をします。
損害賠償請求、債権回収などはもちろん、離婚事件や刑事事件の示談交渉などです。
弁護士が、児童相談所を相手方として行うことは、基本的にこうした交渉と同じです。お一人で進めるより効果的ですし、安心していただけます。
お子さんが突然いなくなった時、ほとんどすべての親は、大きなショックを受けます。
その状態で、役所の組織である児童相談所と対等に話をすることは大変です。
弁護士代理人がいれば、かなり安心できる場合があります。
お困りでしたら、児童相談所との任意交渉をお任せください。
※相談の結果必ず受任するとはお約束できません。
以上が交渉段階の進め方となります。
Ⅱ 一時保護解除のための具体的な方法②・家庭裁判所
次に、話し合いでは解決できない場合の対応です。
児相との話し合いがまとまらず、児童が家庭復帰しない場合の対応として、次のものがあります。
(ご注意)以下は、分かりやすさ優先で書いています。用語は必ずしも正確ではありませんし、法律の条文は省略等していますので、ご注意ください。
1.一時保護解除等の手段
① 法律上の不服申立手段
一時保護されたお子さんを家庭に取り戻す手段のうち、法律に根拠のある方法として次のものがあります。
※一時保護決定通知の下の方に細かい文字で書いてあることが多いです。
ア 審査請求
一時保護を決定した児相の処分の取消を、県庁や市役所の所管部局に対して求める方法です。
イ 取消訴訟
裁判所に対する訴訟手続になります。児相の行った一時保護決定という「行政処分」の取消を求める方法です。
ウ 一時保護(原則2か月)の延長審判
一時保護が長くなり2ヶ月を超えるが、親権者が延長に同意しない場合、児相は家庭裁判所に審判を申し立てます(児童福祉法第33条)。
児相が申立人となり、親権者らは相手方となります。
同意しない親権者らは、家裁で言い分を伝えることができます。
【参照条文 児童福祉法第33条】※一部省略しています。
第3項 一時保護の期間は、一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
第4項 前項の規定にかかわらず、児童相談所長は、引き続き一時保護を行うことができる。
第5項 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが親権を行う者の意に反する場合においては、家庭裁判所の承認を得なければならない。
② 法的手続きの限界
(審査請求、訴訟)
まず、アの審査請求やイの取消訴訟は、いずれも時間がかかります。
審査請求等の手続きが進む前に、児相が、児童を施設入所の有無について検討し結論を出す期間(2ヶ月)が経過してしまいます(一応の結論はもっと早く出していると思われる。)。
施設入所等に進むと、既に一時保護は解除され一時保護処分はなくなっているので、一時保護について不服を申し立てることや、取消訴訟を提起することはできません(存在しない処分だから)。
労力に対して効果が乏しい可能性が大きいです。
そもそもアの審査請求は、中の人である行政が判断しますので、結論が変わることがほとんど期待できません。
完全な事実誤認ケースを除き、一時保護決定通知書に記載のアまたはイの不服申立方法を選択することは、お勧めしません。
なお、児相(児相を管理する自治体)に対して、事後に損害賠償を求める制度があります。
国家賠償法に基づく手続きで、地方公共団体に対しても適用があります。
ただし、あくまでも事後的に金銭的な補填を受けられるだけです。
(33条審判)
次に、ウの「33条審判」です。
当事務所は、親権者から見てあまり意味があるとは思いません。認められるケースはごく例外的だからです。
ただし、メリットはあります。
それは、審判に際して、児相が裁判所に資料を提出することです。
親権者は、これを読むことで、はじめて何が起こっているのかが分かります。
身に覚えのないケースの場合は、延長を不同意にしてください。
ただし、あくまでも例外です。
繰り返しますが、33審判申立について、裁判所が児相の申立を却下することはほとんどありません。
児相は、主に、さらに調査することが必要と判断して、家庭裁判所に一時保護の延長を申し立てます。
延長の審判は、即時の判断を求められるため、児童と面会するなど、十分な事実調査することはありません。
児相の作成した書面、つまり、児相職員が児童を観察した報告書や心理調査の結果報告、事故は場合は医師作成の診断書や意見書等が、主な判断材料となります。
一般的に行政が作成する書面は、行政機関が決定する内容に沿った、もっともらしい理由となる事実が記載されます。
児相が作成する書面には、一時保護延長が必要な理由、施設入所が児童福祉に最善である理由が、もっともらしい理由をつけて書いてあります。
書面を読めば、施設入所はやむを得ないと思えるような書面です。
ですから、保護者、親権者については、ネガティブなことがたくさん書いてあるはずです。
審判に添付される報告書を読んだ保護者親権者は、悪いことしか書いてない、ここまで酷くないと思うことが多いです。
行政が積極的に事実と異なった資料を作成することは、現在の日本ではほとんどないと見なされています。
実際、ほとんどありません。
ほとんどないから、あればニュースになります。
それだけ例外的だということです。
事実の一部を取り上げ誇張することはあるかもしれません(私見では普通にあります)。
しかし、公務員は、書面に嘘は書かないものです。
裁判所が「一時保護延長の必要性がない」と判断することは、事実誤認が直ちに明らかなケース等を除き、ありません。
以上の理由で、弊所は、一時保護自体や、一時保護の延長を法的に争うことは、重要な事実について誤認がある場合を除き、効果がないと考えています。
(2)一時保護の次のステージで争う方法(家庭裁判所の28条審判)
① 28条審判について
一時保護された児童ですが、1週間から10日程度で一時保護が解除される場合もあります。
全国平均は31日程度のようです。
施設入所の場合は2か月近くになることも多いので、家庭復帰の場合は1か月も経たずに戻ってくることが多いと思われます。
2週間を超え、3週間、1か月近く子どもが帰ってこず、児相から解除についての話がない場合は、施設入所が心配になってきます。
施設入所の場合は、一時保護後1か月近く経過するころ、児相の職員が施設入所への同意を打診することが多いようです。
一時保護中の調査に基づき、施設入所がふさわしいと結論したうえでの打診です。
児相によって会議名が異なりますが、児童の処遇を組織決定する会議が、定期的または臨時的に開催させれています。
なお、一時保護直後の段階で施設入所しかありえないと判断される場合もあります。
かなりひどい虐待ケース、親権者の反省が皆無のケースのほか、児童本人が大きな問題を抱えているケース等です。
私自身は、児相は、かなり早い段階で方針決定しているように思っています(見込捜査的な)。
親権者が同意しないと、児童相談所は、次のような趣旨の話をして、同意を求めることもあります。
「同意すれば児童と面会できますが、同意しないなら難しい、、、」
この段階で、子供と面会できない期間が長期化することをおそれ、同意する方も多くおられます。
親権者が同意しない場合、児童相談所は、家庭裁判所に対して、「親権者の同意に代わる承認」を得るための審判を申し立てます(児童福祉法第28条)。
申立があると、家裁で、双方の言い分を主張することになります。
【児童福祉法第28条1項1号の概要(一部省略及び関係条文の挿入をしています。)】
・保護者が児童を虐待し、著しく監護を怠り、著しく児童の福祉を害する場合において、
・保護者の同意がないときは、
・児相所長は、家庭裁判所の承認を得て、
・児童を小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させることができる。
なお、児童相談所は、28条申立てと併せて、家庭裁判所に対して親権停止の審判を申し立てることがあります。
児童に対する医療的な措置が必要なケース等で、行われることがあるようです。
② 28審判の手続
審判は民事訴訟とは異なりますが、調停のような「話し合い」とも異なります。
児相は、児相を申立人、親権者を相手方として、家庭裁判所に、書面で審判を申し立てます。
親権者は、「申立に対する意見書(答弁書)」の提出を求められます。
審判手続きは、書面中心であること、証拠の重要性など、どちらかというと、話し合いである調停よりも、訴訟に似ています。
児童相談所は、親や家庭から分離させて児童を施設入所させる必要性があることを、書面で裁判所に説明していきます。
児童との面談記録、心理的調査(心理士、医師)、親権者との面談記録、保育所や学校関係者に対する聴取概要報告、怪我についての医師の診断書や意見書、その他一時保護中に調査・収集した資料を、証拠資料として裁判所に提出します。
施設入所に同意しない親権者は、ご自分の言い分を家庭裁判所に対して説得的に主張していく必要があります。
児相の申立て書面には、方針決定した内容(施設入所等)に沿った、もっともらしい理由となる事実が強調されて書いてあります。
28条審判に添付された報告書を読んだ大抵の保護者親権者は、悪い点しか書いてない、ここまで酷くないと思うことでしょう。
そして、児相を非難する意見書を提出してしまいます。
しかし、主張すべきなのは、些細な事実ではなく、もっと骨太な、家庭が安全な養育環境であるかどうかです。
児相の対応に文句を言っても、意味がありません。
ポイントが外れた反論をたくさん見てきました。
ポイントを外さないためには、専門家の支援が有効な場合が多いように思います。
審判手続きの中で、家庭裁判所の児童に対する専門的な知識のあるスタッフ(家裁調査官)が、児童や児童が通っていた施設関係者等と面会調査を行う場合が多くあります。
審判手続きでは、審問の日が設定されます。
裁判官が、親権者に対して直接質問します。
弁護士は代理人として同席しますが、裁判官に対する回答は、まず親権者がしなくてはなりません。
さて、結果です。
児相が行った28条の申立に対して、裁判所が施設入所を認めず、児相の申立を却下することは、多くはありません。
最高裁公表資料「児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情 平成26年1月~12月」
③ 家庭裁判所の審判結果に対する不服申立
家裁の審判に対しては、高等裁判所に、審判の取消と元の申立の却下を求めて即時抗告することができます。
大阪、兵庫など近畿エリアは、大阪高等裁判が対応します。
即時抗告が認められる可能性は、低いのが実態です。
2022年中、弊所で3件即時抗告しましたが、全て認められませんでした。
事実認定については、家裁よりもずっと精緻な印象で、児相の報告書を無批判に引用することは無いように思いますが、結論が変わることは、非常に少ないです。
(3)家庭裁判所の審判が確定した後の手段
① 児相との話し合い
児相との面談等、話し合いの再開となります。
② 法的に争う方法
施設入所そのものも行政処分なので、その取り消しを求めて争う方法はありますが、ハードルが高いです。
(4)損害賠償請求
違法な面会交流に対して損害賠償請求し、裁判所で認められる事例があります。
児童相談所は地方公共団体が運営する機関なので、違法な面会制限などに対しては、国家賠償法に基づく慰謝料請求なども考えられるところです。
ただし、仮に、児相の判断に客観的に間違ったところがあったとしても、違法性がないとして認められないことはあります。
立証のハードルは高いケースが多いと思われます。
費用
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 |
1.通常の法律相談 初回は原則定額11,000円(1時間程度)。1時間30分を超過する場合、追加30分まで5,500円(税込)加算 2回目以降は30分11,000円(税込) ※法律相談は原則対面です。ただし、遠方の方については、事前にメール等で日時調整の上で、初回から電話相談可。 ※無料相談は行っておりません。また,受任前には,電話相談及びメールでの具体的な相談には対応しておりません。 ※行政事件は、交渉段階では法テラスの援助対象となりません(2022年12月現在)。児相問題は、児相との交渉協議が一番重要ですので、法テラスでの取り扱いはできません。
2.継続相談 ご自分で児童相談所と協議をなさる場合に、面談または電話で継続的にご助言を差し上げるサービスです。なお、書面作成は致しておりません。 【費用】手数料165,000円(税込) ※初回相談料を含みます。初回相談後にご依頼の場合は154,000円(税込) 一時保護解除または28条審判申し立てまで。一時保護延長の場合は、延長時に55,000円(税込)追加。 |
| 着手金/成功報酬 |
児童の一時保護解除、28条審判への対応 ❷不服審査・家庭裁判所の審判 標準金額 44万円(税込)~ ※❶から引き続きの場合は、11万円(税込)を加算、❷のみの場合は33万円(税込) ※継続相談から引き続きの場合は、22万円(税込)
※高等裁判所への即時抗告のみの対応は、現在お受けしていません。
(2)報酬金 (3)実費・日当 交通費、郵送料、家裁への申立てについては印紙代金等の実費をお願いしています。 また、児相での面談等、出張に伴う日当をお願いしています(基本:3回目以降1回22,000円。関西圏以外は2回目以降1回33,000円)。 |
| 実費 |
交通費や郵便代,裁判所に納める費用その他の実費は,ご負担をお願いしております。 遠方の児相への出張等では,交通費とは別に日当をお願いすることがあります。 (基本:3回目以降1回22,000円。関西圏以外は2回目以降1回33,000円)。 |
| ※ご注意 |
児童相談所案件は,相談者の意向がお子さんの福祉にとって適切ではないと判断できる場合は受任できません。あらかじめご了承ください。 |
※無料電話相談はお受けしておりません。